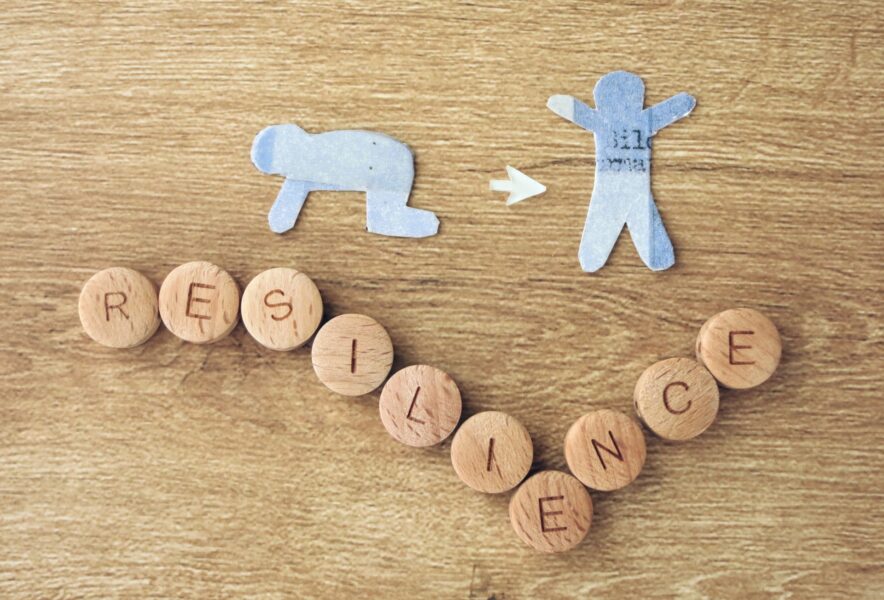チームレジリエンスとは?
レジリエンスとは、逆境やトラブル、強いストレスに適応し、立ち直る力のことです。強風にも折れずに柔軟にしなる木や、倒れても何度も起き上がるおきあがりこぼしをイメージしていただくとわかりやすいと思います。
そして、チームレジリエンスとは「チームが逆境に適応し、回復し、成長する力」を指します。チームレジリエンスが高いチームは、困難や逆境に直面しても柔軟に対応し、そこから得た学びをチームの成長につなげることができます。一方で、チームレジリエンスが低いチームは、困難を解決したり適応することができず、うまくいかないことを誰かのせいにしたり、組織のせいにしたりする傾向があります。その結果、新しいアイデアやチャレンジが生まれず、成果にも悪影響を及ぼす可能性が高くなります。 では、チームレジリエンスが低下する背景にはどのような要因があるのでしょうか。
チームレジリエンスが低下する背景
現代はVUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguityの頭文字を取ったもので、変動性、不確実性、複雑性、曖昧性が高い状況)の時代と呼ばれています。新型コロナウイルスによるパンデミックを経験したように、これからどうなるのかわからない、何が起きているのかわからない、さらには自分が何をしたいのかわからない、という状況に陥りやすいと言われています。
さらに、私たちの価値は何か? 働く意味は何か? こういった、曖昧ではっきりしない、わからない環境が現代のストレスを増大させている一因だと考えられます。
そして、医療・介護業界もこのような時代の影響を受け、ストレスが強くなりやすい状況だと考えられます。具体的には、医療技術や制度の急速な変化、感染症の流行やそれに伴う業務の増加、不確実な政策変更への対応が求められ、従業員の負担が増大しています。さらに、人材不足や高齢化といった長期的な課題も重なり、現場では一人ひとりが多くの責任を担わざるを得ないため、精神的・肉体的なストレスが溜まりやすい環境となっています。
このような状況が長く続いた結果、職員は自身のストレス感情を軽減することを優先し、批判的、攻撃的、他責的、逃避的、欺瞞的な言動や行動を取るようになります。例えば、問題が生じた際に、犯人探しをしたり、責任を他者に押し付けたり、組織のせいにするような言動や行動が見られるようになります。また、欺瞞的コミュニケーションも増加します。欺瞞的コミュニケーションとは、事実を歪めて伝えたり、相手が意図的に誤解するように仕向けたりする行為を指します。具体的には、嘘をついたり、事実を隠したり、曖昧な表現を用いて真実をぼかすなどの行動が含まれます。その結果、職員間の信頼関係が大きく損なわれてしまいます。
さらに、怒りの感情を露わにして相手をコントロールしようとしたり、ハラスメントに発展したりするケースも見られます。また、他の職場を探すといった行動につながり、離職率が高まることもあります。このように、個々のストレスに対する様々な行動(批判的、攻撃的、他責的、逃避的、欺瞞的)が、信頼関係を悪化させ、チームのレジリエンスを低下させるといった、悪循環を引き起こしてしまうのです。では、どうすればチームのレジリエンスを高めることができるのか、そのための要素について解説していきます。
チームレジリエンスを高める最も大切な要素
チームが順調な時、予想外の事態が起きた時、困難に直面した時、どの状況でも逆境を乗り越えて成長を続ける強いチームには、どのような共通点があるのでしょうか。
それは、「互いを認め合い、信頼し合える関係性」です。
もちろん、チームレジリエンスを高めるための重要な要素は他にも多くありますが、今回はその中でも最も重要な「関係性」に焦点を当て、チームレジリエンスを向上させるポイントについてご紹介いたします。
レジリエンスが高いチームの「関係性」
●ポイント①「チームの一体感」
レジリエンスが高いチームの関係性のポイント①、それは「チームの一体感」です。チームの一体感が高まると、社員同士が支え合い、困難に直面しても力を合わせて共に乗り越えようとする姿勢が強まり、チーム全体の成長へとつながっていきます。
チームの一体感を高めるポイントは、まず共通の目標やその達成までの具体的なシナリオを共有し、全員が同じ方向に進んでいくこと。また、メンバー一人ひとりの個性や強みを理解し、お互いに認め合う風土をつくることで社員間の信頼関係が強まります。
さらに、成功や失敗に対して感情を共有し、喜びや悔しさを共に感じ合うことで、チーム内の絆が深まり、より協力的なチームへと成長していきます。
●ポイント②「心理的安全性が高い」
チームレジリエンスが高いチームの特徴の一つに、「心理的安全性の高さ」があります。心理的安全性とは、チーム内で自分の意見やアイデア、ミスを率直に共有しても批判や否定を受けないという安心感のことです。
チーム内で強い批判や攻撃、失敗への過度な恐れ、または過剰な忖度が存在すると、協力して困難を乗り越えるための雰囲気が生まれません。逆に、社員が自由に意見を言い合い、失敗を恐れず挑戦できる環境が整っていれば、個の力を最大限に発揮し、お互いに協力し合い、チーム全体で困難を乗り越える力へとつながっていきます。
●ポイント③「存在承認=リーダーがちゃんと見てくれている」
最後は、「リーダーが自分たちをちゃんと見てくれている」という感覚です。これは、メンバーの存在そのものに価値があることを認める「存在承認」につながります。社員一人ひとりがチームにとって価値があると信じられ、個々の努力に目を向けてもらえることで、社員は自信を持ち、積極的にチームに貢献できるようになります。
反対に、リーダーが社員の頑張りに気づこうとせず、理解しようとしない態度で接している場合、褒められても素直に受け入れられなかったり、叱られても反発心を抱いたりするだけかもしれません。
「リーダーが自分たちをちゃんと見てくれているという感覚」は、チーム内に安心感と信頼関係を生み出し、結束を強めます。これにより、チームは困難を乗り越えられるレジリエンスを育み、目標に向かって前向きに努力しようとする雰囲気が生まれます。
「関係性」に焦点をあてたチームレジリエンス向上の実践について
●実践方法①「サンクスカード」
始めにご紹介するのは、感謝を伝える「サンクスカード」という活動です。サンクスカードとは、感謝を伝えるためのカードで、手書きでメッセージを記入し、ポストに投函すると、相手に届く仕組みになっています。このカードは社内の誰にでも書くことができますし、例えば、投函されたカードを壁に貼ることで、感謝の気持ちをチーム内で「見える化」することも可能です。
サンクスカードを取り入れることで、自己重要感や会社への貢献感、そして、リーダーがちゃんと見てくれているという感覚が高まります。また、「あなたがいてよかった、ありがとう」といった感謝の言葉は、「あなたには価値がある」という「存在承認」へとつながります。
さらに、ほかの社員の良いところに気づき、それを伝えるきっかけにもなります。その結果、「ありがとう」や「嬉しい」といったポジティブな感情を社員間で共有することができます。サンクスカードの導入は、社員間の信頼関係や協力関係を築き、チームレジリエンスの向上につながります。
●実践方法②「対話の時間をつくる」
次にご紹介するのは、「対話の時間をつくる」という取り組みです。具体的には、朝礼や会議後にテーマに沿って小グループで対話を行う時間を設けます。例えば、困難だった出来事を振り返る対話を通じて、事実と向き合い、困難に対処するときの良かった点や困難から得た気づき、学びを共有することができます。その結果、対話から新たな教訓を得ることができ、個人やチームの成長につなげることが可能になります。
他にも、理念を再考する対話では、自社の理念や行動指針をもとに対話を行うことで、働く意味の共有や共感へとつながっていきます。また、Well-being(幸福感)を高める対話では、仕事で感謝したことや社員の良い所をテーマに対話することで、働きがいを感じたり、自分らしさに気づくきっかけにもなり得るでしょう。
このように、対話の時間をつくることを習慣化することで、お互いの感情や価値観、働く意味の共有・共感が促進され、多様な視点が重視される文化が醸成されます。また、対話を通じてお互いを知り、認め合い、尊重し合うことで、チーム内の心理的安全性が高まります。さらに、困難だった出来事を振り返る対話から、新たな教訓を学ぶことができ、チームの成長にもつながっていきます。これらの結果、職員間の信頼関係や協力関係が構築され、チームレジリエンスの向上につながっていくでしょう。
「早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行け」
これはアフリカのことわざです。一人ならば素早く行動ができますが、達成できる目標には限界があります。一方、仲間と共に進む場合、みんなのペースに合わせるためスピードは遅くなるかもしれませんが、個人では到達できない遠い目標や未知の場所に向かって進むことができます。お互いを支え合い、補い合い、力を合わせることで強い信頼関係が生まれ、それによって個々の限界を超える「チームレジリエンス」が育まれ、チームメンバー全員の成長につながっていくのではないでしょうか。