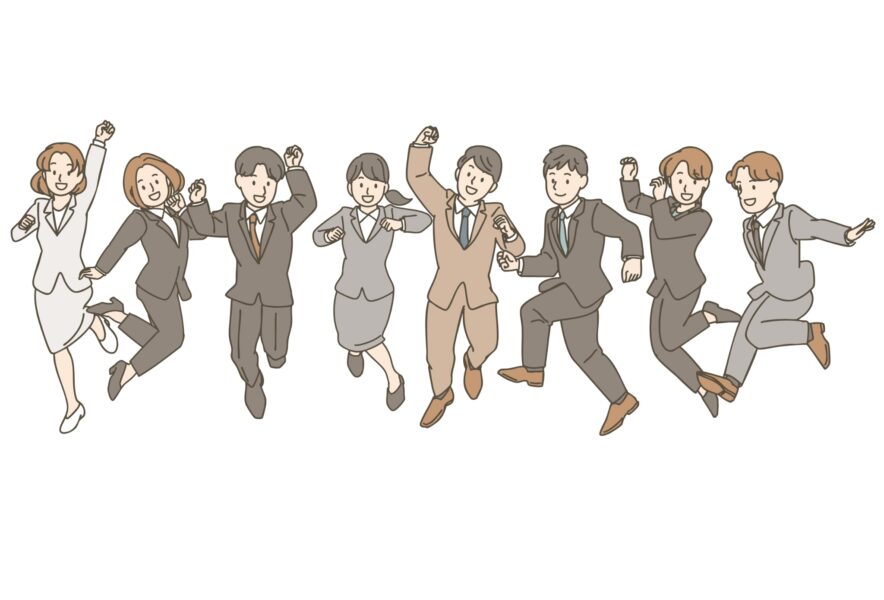いま世界で注目される「ポジティブ心理学」
ポジティブ心理学は、人間がより良く生きるための強みや資質、希望、感謝、レジリエンスといった“幸せ”に光を当てる心理学です。従来の心理学がうつや不安などの課題解決に主眼を置いてきたのに対し、ポジティブ心理学は「何が人をよく機能させ、幸せにするのか」を体系的に研究します。
研究では、ポジティブな資質を育むことで、主観的幸福感の上昇、創造性と生産性の向上、身体症状の軽減、人間関係の質の改善、さらには周囲への良い波及効果(“ブロードン&ビルド”)が報告されています。ハーバード大学で関連講座が人気を博したことも象徴的で、いまや教育・医療・ビジネスの各分野で展開されるようになりました。
「ポ活」とは?—ポジティブな心を育む習慣づくり
朝活、婚活、美活…そして「ポ活」。ポジティブな心を“活動として育てる”取り組みの総称です(私が考えました笑)。ここでは、とくに幸福との関連が強い「感謝」に焦点を当てた実践を3つ紹介します。どれも特別な道具は不要、今日から始められます。
どれも特別な道具は不要、今日から始められます。
【ポ活その1】感謝をシェアする「ポ活タイム」
ねらい: 感謝に意識のピントを合わせ、職場・家庭に温かい循環を生む。
やり方: 週1回、4~5人で輪になり、一人1~2分「最近の感謝・うれしかったこと・学び」を口頭で共有します。話す順番を決め、発言は否定せず拍手で称え、質問は「もっと聴きたい!」という好奇心ベースに。内容は職場・利用者さま・家族・私生活、なんでもOK。
効果のポイント: 回を重ねるほど、日常の中から“良いことセンサー”が働き、感謝が習慣化していきます。良いことセンサーをみんなで育てる時間が、メンバー間の前向きな感情を生み出し、信頼関係を支えてくれます。
すぐ使えるテーマ例:
「この一週間で“ありがたい”と感じた小さな瞬間は?」
「誰かの優しさに気づいた場面は?」
「自分をちょっと褒めたい点は?」
NG例: 反論・評価・説教。発言の“正しさ”より“温かい雰囲気”を大切に。
家族版: 夕食後に3分。夫婦関係が良くなり、子どもは“良いこと探し”が得意に。自然と家族内の会話量が増えます。
【ポ活その2】Three Good Things(3つの良いこと)
ポジティブ心理学の提唱者マーティン・セリグマン博士が開発したシンプルなワーク。一日の終わりに「今日の良いことを3つ」と「そう感じた理由」を書くだけ。
続けるコツ: スマホのメモでもOK。寝る前のルーティンに組み込む。“小さな良いこと”で十分(晴れた、笑顔で挨拶できた、コーヒーが美味しかった)。
臨床・介護現場への広がり: 理学療法士・藤生大我先生は、認知症家族介護者への「ポジティブ日記(よいこと3つ+理由+自分をほめる言葉)」を導入し、介護負担感だけでなくBPSD低減にも効果があることを報告しています。介護者の意識が“できていること”“助けられていること”へ移ると、言葉が柔らかく、接し方にもポジティブな変化が生まれるからだと考えられます(詳細は「藤生大我研究室」で検索、日記テンプレートのダウンロード可)。
職場での導入を成功させる7つのポイント
①活動を行う主旨を明確にし、共有を丁寧に行う
②リーダーがまず実践:率先垂範が何よりの合図。リーダーが積極的に取り組むことで空気が変わる。
③活動のルールは皆で合意して進めること。
④マンネリ防止:週によって「○○強化週間」などイベントを作る
⑤参加のしやすさ:否定や茶化しはNG。“話さない参加”もOKから始める。
⑥振り返りの場:活動をやってみた感想や、学んだことなどを共有する場をつくる。
管理者・リーダーとしてできること
ポ活を職場に根づかせるためには、管理者やリーダーの役割がとても重要です。現場の雰囲気を変えるのは制度や仕組みだけではなく、「人が人に与える影響」だからです。まず大切なのは、リーダー自身がポジティブな姿勢を示すこと。コミュニケーションの中に一言「ありがとう」を添える、会議の冒頭で「最近の良かったこと」を共有するなど、小さな実践を見せることが最も効果的なリーダーシップになります。そのようなリーダーの言葉や行動が伝わり、周囲は安心してポ活に参加できるようになります。
次に必要なのは、場のデザインです。職員が無理なく参加できる仕組みを整えることが重要です。例えば「ポ活タイム」を朝礼に組み込む、Three Good Things を共有する掲示板を用意するなどです。ルールを押し付けるのではなく、職員が「ちょっとやってみようかな」と思える雰囲気をつくることが大切です。また、形式的にならないように、テーマを変えたり、発表スタイルを工夫したりすることでマンネリ化を防ぎます。
さらに、成果を見える化し称えることも管理者の役割です。素敵な感謝エピソードを職員会議で紹介する、ポ活によって生まれた小さな成功事例を発表するなど、努力が認められる機会を設けることで職員のモチベーションも上がっていくでしょう。「物語」で共有することで、チーム内に温かい雰囲気が生まれます。
また、学びの場を提供することも有効です。ポジティブ心理学や感謝の研究成果を勉強会で紹介すると、なぜ効果があるのか納得でき、活動をすることの意味が生まれ、より継続しやすくなります。科学的な裏付けは、現場の抵抗感を和らげ、日常の実践に意味を与えてくれます。
最後に、リーダー自身が「失敗してもいい、まずやってみよう」という姿勢を持ち続けることが何より大切です。ポ活は一度で完璧に定着するものではありません。小さな一歩を重ね、続けることが文化を生みます。管理者が率先して心を開き、感謝を伝える存在となることこそが、組織を前向きに変えていく最大の推進力になるのです。
心をひらき、より添い、伝えること
私たちは人生の中で、かけがえのない人たちと出会っています。自分を肯定し、人を思いやることができるのは、愛に触れる経験があるからです。抱きしめられた時の温もりは今も心の奥に残されています。意思をもち、希望をもって前に進めるのは、ほめられたり、応援されたり、一緒に壁を乗り越えたり…そういう経験を共にした仲間がいたからです。人と繋がり、結ばれ、幸福や愛情を感じることができるのは、いつも近くにいてくれる、大切な人がいるからです。恋愛や結婚、友情。そして仕事仲間や利用者様との出会いは人生を豊かにしてくれます。
幸せを感じながら人生を歩むこと。それはいま在るものに感謝すること。
『あなたがいてくれてよかった。ありがとう』
近くにいる方へ、利用者様へ心をひらき、寄り添い、伝えることで、希望が生まれ救われる人がいます。
令和の時代。人々が美しく心を寄せ合う中で、新しいポジティブな文化をみんなで創っていきませんか。
引用文献
藤生大我・山上徹也・山口晴保(2018).認知症家族介護者がポジティブ日記をつけることの効果.日本認知症ケア学会誌, 16(4), 779–790.